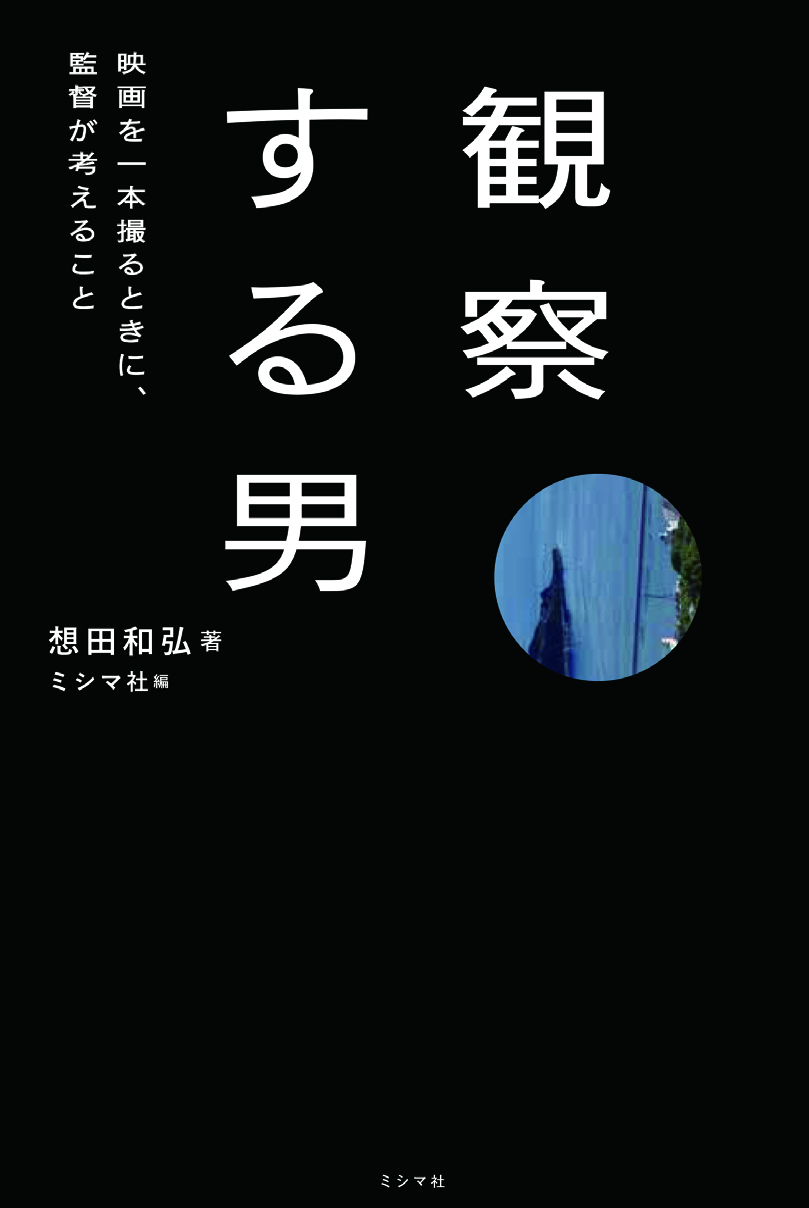本の詳細
舞台は牛窓(岡山県)。カメラを回せば----
グローバリズム、高齢化、震災の影響、第一次産業の苦境・・・
すべてが映りこんでいた。
観察映画『牡蠣工場』(2016年2月公開)をつくる監督を逆観察。
台本なしの映画づくりの幕が上がる!
映画を観るように読んでください----編集部より
〈内澤旬子 /ルポライター〉
文字で綴るノンフィクションで、手法が斬新で面白いと思うことは、なかなかないです。映画を撮って編集している途中にはさむインタビューだからこそ聞き出せた言葉ばかりだと思う。
〈岸政彦/社会学者〉
なるほど! こうやって撮ってるのか!! 「観察映画」の作り手が語る、観察する身体の技法。これは、物語が生まれる瞬間の物語だ。
〈堀部篤史/誠光社(書店)店主〉
言いたいことや、結論があって映像を撮りはじめるのではなく、とりあえず撮影した素材をじっと眺めることで意図せざる物語が浮かび上がる。私たちが普段一瞥もくれることなく通り過ぎる街頭の選挙演説や、片田舎の水産工場にも背景や奥行きがあり、物語があるということを「観察映画」は教えてくれる。分かりやすい結論を提示しなければ商品として成立しないという幻想のもと、つまらないクリシェが量産される中、想田監督のものの見方は、ドキュメンタリーという狭いジャンルを超え、あらゆるメディアに関わる人間が身につけるべき「眼鏡」のようなもの。何を語るかではなく、どのように語るかに、映画にせよ本にせよその本質があるのだから。
目次
本書について
I
1 舞台はなぜここなのか?
想田和弘監督 フィルモグラフィー
II
1 誰に密着するのか?
2 登場人物を増やすか?
3 どうすれば「映画」になるのか?
《コラム》牛窓、台湾、秘密保護法案
III
1 何でどう撮るのか?
2 編集の目的は何か?
3 どうすれば監督になれるのか?
4 生計をどう立てるのか?
5 映画づくりにとって、何がムダか?
映画『牡蠣工場』あらすじ
IV
1 何を残し、何をカットするのか?
2 編集の基準は何か?
3 「何の」映画なのか?
4 被写体には観せるのか?
V
1 映画祭ではどうすれば上映されるのか?
《コラム》ロカルノから見える日本の風景
あとがき
編集後記